本来ならお盆を過ぎると、景色のなかにトンボがまじり、秋を感じさせる風が吹いて、夏の終わりが来たなあ..と、しみじみするわけですが、天気予報を確認しますと、9月6日を過ぎても最高気温が34℃と書かれています。
僕(@kazuaki_TANI)などは、空調が効いた涼しい部屋でパソコン作業をすることが多いものですから、まだ救われております。気候についてもう少し書きますと、埼玉県南西部は雨が降りません。台風もやって来ません。近所の畑を見渡すと、里芋の大きな葉っぱが萎れていますし、農作物への影響が大きいことは簡単に予想できます。昨年は、米が不作で大変なことになっていますから、野菜と米の価格上昇は今後もつづくかと思われます。
昔の人じゃありませんが、雨乞いが必要だと感じるこの頃です。
この猛暑が、人間の活動によるCO2排出、肉食による畜産の増加、都市化(アスファルトとコンクリートの増加)の波、森林伐採等が地球温暖化の原因であると前の記事で書きました。

猛暑で疲れた時には家から近くのムーミン谷でひと休みしている。
そして、このまま改善されなければ気温はさらに上昇することが大多数の専門家によって予測されています。痛い目にあわないと修正できないのが僕たち人間とはいえ、毎日毎日、こう暑くてはさすがに温暖化を食い止めよう!という気概が生まれてもおかしくはありません。
しかし、実際は政府と大企業が温暖化を阻止するのための動きを見せているものの、日本ではまだまだ環境への意識は低いのが現状のようです。もはや日本の四季は大きく変貌してしまい6月〜10月が夏ですら、かき氷屋とアイス業者がますます儲かるってわけです。
一方で世界を見渡しますと、スペインのバルセロナ市で革新的な都市計画が進行しています。これについて映像クリエイターの高城剛さんが現地から分かりやすく伝えています。
今週は、バルセロナにいます。
あちこち回ってバルセロナに戻ると、人が中心にいる街づくりが徹底しているな、と感じます。訪れた多くの観光客は、サクラダファミリアや活気ある市場、地中海ビーチに惹かれると思いますが、目抜通りであるランブラスやランブラ・カタルーニャなど街の中心に位置するストリートは、往来の真ん中を人が通り、車は側道を通る設計になっているのが、世界のどの都市とも違います。
バルセロナの象徴であるランブラス大通りは、18世紀に旧城壁跡を歩行者のプロムナードとして整備したのが始まりで、全長およそ1.2kmの並木道の中心部を人々が闊歩出来る構造を今も残しています。
観光客も住人も道の真ん中を思い思いのペースでそぞろ歩き、花屋やニューススタンドに立ち寄って、オープンカフェで語らい、ストリートパフォーマーに拍手を送るのが日常風景です。ここは単なる移動のための通路ではなく、出会い、交流し、時間を過ごすための「巨大な公共のリビングルーム」であり、この設計思想はバルセロナの都市計画の根底に流れる「人を中心とした社会」の精神を象徴しているのが、よくわかります。
また、カタルーニャ広場からグラシア通り方面へ向かうランブラ・カタルーニャ通りも同様、中央に広大な歩行者専用の並木道が設けられ、その両脇を車道が走る通りを見ると、もともと「人」こそが街の主役であると、雄弁に物語っています。
しかし、20世紀に入り、世界中の都市がそうであったように、バルセロナも一時期は「モータリゼーション」の波に飲み込まれていきました。
経済成長と効率化の掛け声のもと、街の動脈は次々とアスファルトで覆われ、主役の座は次第に自動車へと奪われていき、かつて人々の笑い声や話し声が響いていた空間は、エンジン音と排気ガスの匂いに徐々に支配されるようになります。これは利便性と引き換えに、都市が本来持っていた人間的な温かみやコミュニティのつながりを少しずつ侵食していく過程でもありました。
こうして出来上がった大企業が主導する車中心社会は、効率的ではあっても、必ずしも人間にとって幸福な空間ではありませんでした。その反省から、市は2024年にランブラス大通りの車線を片側1本へ減らして、舗道と中央プロムナードを拡幅する大改修を開始。すでに第一期工事が完了しました。
そしていま、この失われた「人中心」の街の記憶を取り戻し、現代に復権させようとする壮大な社会実験が、バルセロナで力強く進行しています。それは「スーパーブロック」と呼ばれる都市再生プロジェクトで、これは単なる街の再開発に留まらない「まちづくりルネッサンス」とも呼ぶべき市民運動に他なりません。
スーパーブロックは、19世紀に都市計画家イルデフォンソ・セルダが設計した碁盤目状の3×3=9つの街区(ブロック)を1つの大きなユニット「スーパーブロック」として定義し、車道を歩道に変えて内部の道路への自動車の進入を大幅に制限する大胆な試みで、これまで車が占有していた道路空間を劇的に解放しました。
アスファルトは剥がされ、土が敷かれて木々が植えられ、車道だった場所は、ベンチが置かれた広場や、子どもたちが駆け回る遊び場、地域住民が野菜を育てる菜園、野外卓球台が設置されたスポーツエリアへと生まれ変わりました。
バルセロナ市は、この計画によって都市空間に占める「歩行者用スペース:車道」の比率を「45:55」から「69:31」へと逆転させることを目指しており、これは都市空間の所有権を自動車(そしてそれを推進してきた大企業)から市民の手に取り戻すという、明確な意志を示しています。
2016年に本格導入が始まったポブレノウ地区では、「スーパーブロック」効果は目覚ましいものでした。導入後、自動車交通量は最大で82%も減少し、それに伴い二酸化窒素(NO2)濃度は33%低下、騒音レベルも大幅に改善。何よりも大きな変化は、街の風景そのものです。
エンジン音の代わりに子どもたちの笑い声が響き、排気ガスの匂いの代わりに土や植物の香りが漂うようになりました。高齢者は安心して散歩を楽しみ、若者たちはベンチに座って語らう。
地元の商店街では、人々が車を降りてゆっくりと歩くようになったことで、客足が増え、売上が向上するという経済的な効果も生まれています。
僕も毎朝代表的スーパーブロックのコンセル・デ・セント通りを走っていますが、都市の真ん中なのに、まるで森の中を疾走しているような気分になります。
このように、遠くスペインでは豊かさの価値観が大きく変化しています。環境への意識が高まった市民の意思が、行政を動かし、自動車社会から人と自然が中心の街へと変貌を遂げています。都市部のアスファルトが減り、森林が増えるわけですから温暖化対策としても有効ですし、都市として次世代のモデルとなります。
バルセロナ市は首都マドリードの次ぐ、スペイン第二の大都市が、世界の都市計画と民主主義の模範となっていくと思われます。
心にゆとりがない日本では、このような発想での都市計画はおそらく難しいでしょう。ですので、まずはこのブログを読んでくれている皆さんのように環境や健康への意識が高まった人たちによって、個人レベルでの住空間(地域も含む)の取り組みが期待されます。
そんなわけで、ここから本題です!

地域のマルシェで食べた自家製パイナップルシロップのカキ氷。
猛暑でも快適に暮らせる住空間を自然素材でつくる。
地球温暖化による猛暑は、家づくりにも大きな影響を与えています。
先日、北海道の友人と話をしていると、近頃ではエアコンを設置する家が増えてきたらしく(つまり夏でも冷房は必要なかった)、彼の家もとうとう電気屋で注文してきたらしいのです。青森が実家の親戚も、昔は夏でも朝晩寒くてストーブをつけていたけど、今ではエアコンがないとダメだ、と言っていました。
寒冷地でもそうなのですから、日本の気象観測史上最高気温41.8℃を記録した群馬県ならなおさら猛暑に対応しなければなりません。政府による住宅の省エネルギー基準は、国際的に活発化しているカーボンニュートラル*が目的です。高気密高断熱の基準を厳しくすることで、電気の消費量を減らし、発電時のCO2排出量を抑えようとしています。
エアコンの効きが良くなれば快適だし、電気代も安くなる。それが一般認識でしょう。確かに、省エネ基準を満たした家は、夏も冬も少ない冷暖房(概算で電気代が3割減)でまかなえます。しかし、エアコンには大きな弊害があります。
夏は身体が冷え、血行不良や自律神経が乱れ、結果として免疫が下がります。冬は過乾燥により肌荒れ、喉の痛み、感染症リスクが高まります。
つまり、エアコン使用を前提とした高気密高断熱の家=快適とはいえません。
肌感覚ではエアコンによる涼しさも、温かさも一時的には快適かもしれませんが、それに慣れた瞬間から「不快(微量なストレス)」に変わります。それは、最新のテクノロジーを使った機器でも限界があります。エアコンが苦手な人が多いのはそのためです。
では、どうすれば本当に快適な住空間を作れるのでしょうか?
ヒントになるのが日本の蔵です。

近所にある蔵造りの古民家。
35℃を超える猛暑でも蔵のなかは25〜28℃に保たれます。外から蔵に入ると、冷んやりと感じるほど涼しい!それは、蔵の造り自体に[調湿]と[調温]の効果があるからです。ご存知のように、蔵は外壁、内壁ともに漆喰が使われています。自然素材である漆喰は、調湿性能があって余分な湿気を吸い取り、乾燥すると吐き出す「呼吸する壁」として働きます。
IZANAGIの家は全室(収納内部も)で天然100%な幻の漆喰を採用しています。
人の体感覚は、湿度が高いと同じ温度でも不快に感じます。ハワイや地中海沿岸が、真夏でも心地よく滞在できるのは日本の夏のように湿度が高くないからです。つまりは、湿度を調整していくれる天然の素材を使うことで、エアコンへの依存がさらに低くなるわけです。
さらに、漆喰には調温効果もあります。漆喰の壁は夏の冷房による冷えを蓄え、エアコンをOFFにしても、徐々にその冷温が空気中に放出されるため、急激に部屋が暑くなったり[夏]、寒くなる[冬]のを防いでくれるという働きです。

IZANAGIが採用している音響熟成木材。
そして、もうひとつ!
床材も自然素材にすることで、調湿と調温の効果があります。
特に国産の杉材はその効果が高く、湿度が高い時は杉が水分を吸収し、湿度が低い時には吸収した水分を放出します。無垢材なら何でもいいわけではありません。IZANAGIが推奨するのは、木材の乾燥方法にこだわりがあるものです。
例えば、私たちが使っている「音響熟成木材」は、常温に近い温度でじっくり丁寧に杉を乾燥をさせており、その細胞がしっかりと生きた状態です。塗装もしませんから、木が本来持っている様々な生物的作用を住空間で発揮してくれます。
逆に、安価な無垢材は、高温(100℃以上)で強制乾燥するため細胞が息絶えた状態。大量生産のフローリング材よりはいいかもしれませんが、オススメはできません。
以上のように、室内を本物の自然素材にするだけでも、エアコンへの依存度が下がりますから、快適性を高めるだけでなく、冷暖房病のリスクを下げることができます。
そして実は、猛暑でもさらに快適に暮らせる方法があります。
温度や湿度以外からも、僕たち人間はストレスを感じる生き物である、ということを掘り下げると、さらなる(エアコンに頼らない)本質的な対策が可能になります。
だいぶ長くなったので続きはまた次回にして、今日のところはこの辺で!



















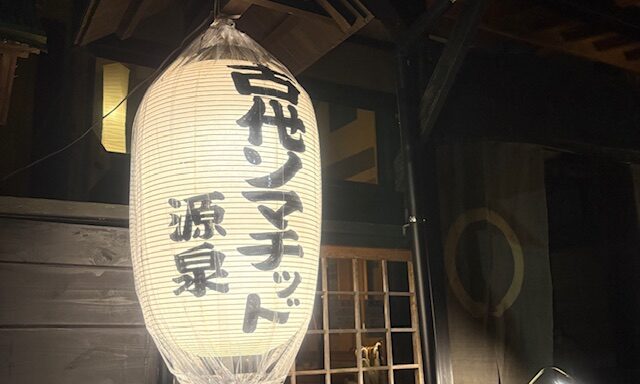






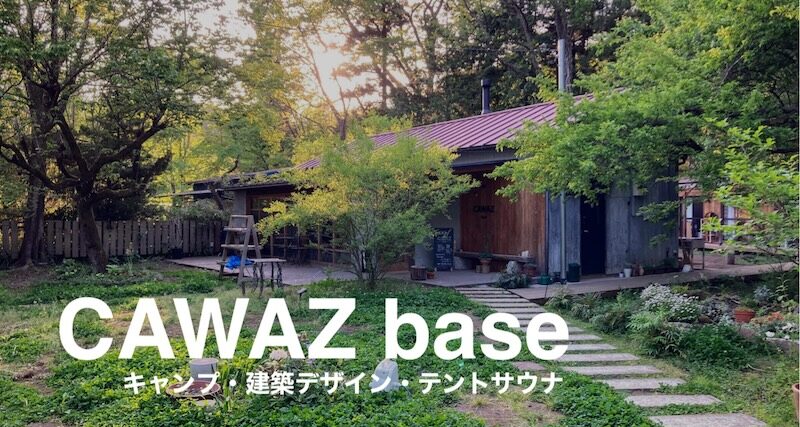



コメント